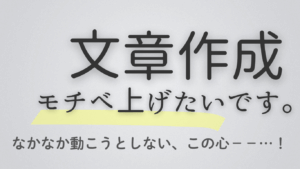文章を書いていると、ときどき思うんですよね。
——言葉が先なんだろうか。
——それとも、心が先なんだろうか。
これは昔、大学の教授が言っていた言葉で、
ずっと頭のどこかに残っている問いです。
人は「感じたから言葉にする」のか。
それとも「言葉にするから感じられる」のか。
少なくとも私は、どちらか一方では説明できないな、と感じています。
● 「心」先行タイプのひと
これは、最初に“思い”が立ち上がり、あとから言葉が追いつくタイプといえます。
雑談時のときの私は、まさにこれです。
「あーでもない、こーでもない」と感情が先に走る。
フォーカスが次へ次へと移っていくので、
話の終着点に着く前に、思いのままに寄り道をしがちなんですよね。
このタイプに適する文章は、おそらく
- エッセイ
- 日記
- 内省
- 小話
- 感性をそのまま置く文
のような“気流のある文章”です。
論理で整えるより、言葉の質感を丁寧に磨いたほうが輝く。
感情をいかに情感豊かに、臨場感をもって魅せるかという点ですね。
短文で一気に書き切ったり、
シリーズ化で流れを作ったりすると映えるタイプですね。
● 「言葉」先行タイプのひと
今度はその逆、
言葉で明示化して枠をつくることで、思索がどんどん広がっていくタイプです。
私が “書く” ときは、完全にこちらですね。
言葉を置いていくうちに、
「あ、私はこう思っていたんだ」と後から気づく。
言葉が心を連れてくるような感覚です。
考察・解説・分析の文章に向いていて、
構成(プロット)を最初に組むと一気に書きやすくなるんですよね。
このタイプはテーマに強いこだわりがなくても大丈夫で、
書いているうちにテーマが育っていくと思います。
だから私は、テーマ決めの補助にAIを使うことも多いです。
(自分では思いつかない切り口が提示されるので、とても助けられます。)
2つは対立ではなく、「循環」の関係
ここが一番大事な部分なのですが、
心 → 言葉
だけでもなければ
言葉 → 心
だけでもない。
文章とは、この二つの往復運動なんですよね。
心が動いて言葉が生まれ、
言葉を書くことで心が深まり、
そうしてまた、そのつぎの言葉が見えてくる。
書く行為は、外に向けた発信というより
自分の内側に「輪郭」をもたせるための作業
なのだと思います。
文章を書き終えると、
“さっきまで曖昧だった自分” が立体的になって現れてくる。
だから私は、書くこと=自分自身を整理するような感覚に近いです。
日記もそうですよね。
書いた後で「スッキリした」という経験もあるのではないのでしょうか?
正解はどこにあるのか?
結論を言えば、正解なんてないんですよね。
ただ、大切なのは
自分はどちらから動くタイプか?
これを知っておくことだと思います。
心が先に動くなら、短文やエッセイで “質感” を磨く。
言葉が先に動くなら、構成をつくって “論理” を磨く。
どちらも等しく美しいし、どちらも文章になる。
つきつめれば文章とは、
”自己が行う思考の軌跡”
なのだと思います。
私が書こうとする理由も、きっとここにあるのかと…
書くことでしか見えないものがあって、
書くことでしか触れられない自分がいて、
書くことでしか整わない何かがある。
だから今日もあしたも、言葉を置いていくのだと思います。
どちらが正しいかではなく、
“どちらが自分を前に進めるか”。
その視点で見ると、文章はすこし自由になるのかもしれません。
この話のつづきは、 「いい文章って誰が決めるのか?」 で触れていきますね。
ではまた。